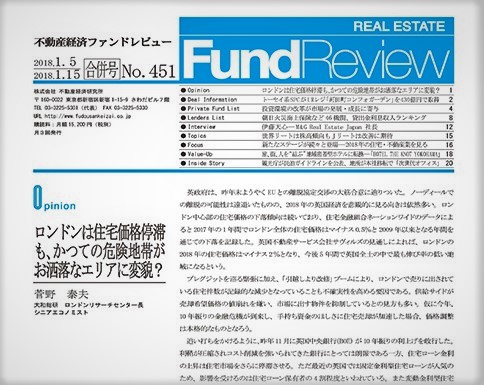2023年のマンション市場は縮小均衡が継続
新業態への拡大・変革をスタートさせる元年
購入者の賃貸脱出志向は強く、エリア・駅距離等、立地面を多少妥協しても「買える物件」を検討する動きは強まっている。しかし、予算上限を超える物件では徐々に販売のペースダウンが始まっている。所得向上が見られない中、郊外は4000万円台中盤まで、近郊は5000万円台中盤までが予算上限であり、これを超えることは難しい。この1年で建築費が2割以上上昇したことで、郊外でのマンション事業は難しくなっている。
2023年は、用地仕入れに関しては23区や横浜、川崎が中心で、近郊・郊外では価格許容力の高い好利便立地に限られてくるため、結果的に需給バランスは良好な状況が継続し、高値水準の市場相場も維持されると見られている。つまり、2023年の首都圏マンション市場は、2022年から引続き縮小均衡が継続する。新築マンション市場の好立地志向が強まる一方で、マンション用地自体が少ないため、デベロッパー各社はマンション用地を自ら創り出す動きとして、建替え、再開発、等価交換事業に取り組んできた。その成果が上がり始めており、都内だけで総戸数2万戸を超え、首都圏全体で約2万8000戸とも言われている。
再開発・建替え事業を巡っては、市街地再開発法と建替え円滑化法の改正・整備で地権者の合意形成のハードルが低下している。また、木密地域の不燃化・震災対策や駅前広場の整備など行政の再開発に対する姿勢が強化され、市場相場の大幅上昇により還元率等で、地権者メリットが増加している。このため、再開発の事業期間が以前の「10~20年」から「5~10年」程度に短縮されてきている。これまで再開発・建替え事業の取組みで高いハードルとなっていた開発期間の長期化によるデベロッパーリスクの増大が、期間短縮により解消されてきた。今後、さらに再開発手法が普及・拡大していけば、23区や郊外駅前でも再開発・建替えによるマンション事業はさらに加速していくと見られている。
年初から賃金のベースアップが大きな話題となり、低成長・デフレ経済からの転換に期待が高まっている。インフレ経済化では、希少性の高い都内都心の不動産マーケットの安定成長が描ける。ただ、都心部は良くても郊外実需向けのマーケットに関しては、一般層の所得が向上し購入予算をアップさせるまでにはあと2~3年は要するため、分譲マンション市場はこの先1~2年は縮小均衡とならざるを得ず、「デベロッパーにとっても我慢の年となるのではないか」(杉原氏)。
それを先取りしてか、デベロッパーが他業種とのコラボレーションによって、不動産ビジネスの拡大を模索したり、自社の開発商品に新しい付加価値を追求し始めている。三井不動産は、「東京ミッドタウン八重洲」で事業創造の機会を提供する専用施設を設け、地域経済創発の新規事業に取り組む。三菱地所は貸会議室事業会社を買収、コワーキングスペース等、フレキシブルオフィスの出店を加速、野村不動産は教育サービスの「やる気スイッチ」と資本業務提携、学童保育などのキッズ向け事業を強化する。タカラレーベン、フージャースコーポレーションは地方都市(企業・行政)とのコラボで地方再生(再開発)事業、サンケイビルは関西テレビと共同で都市型データセンター事業、東急不動産も再生可能エネルギー発電事業の専業の資本業務提携し、再生可能エネルギー事業を強化するなど、今後の事業環境の変化に向けて新しいポートフォリオの構築に取り組み始めている。2023年~2024年のマンション事業は、価格許容力のある好立地を中心に吟味しながら取り組んでいく必要があり、デベロッパー各社にとって、新世代に向かって新しい業態への拡大・変革をスタートさせる元年となるのではないかと見られている。